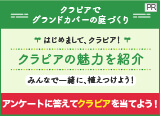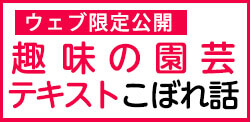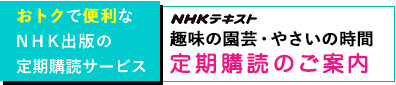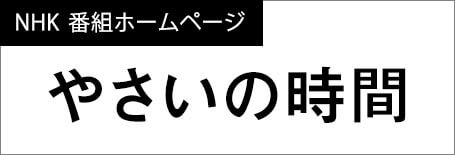イラガ
善林六朗[園芸研究家]
- 初期症状
- 葉に、白い斑点や白く透けた部分が生じ、それらの周辺の葉にとげの生えた幼虫がいる。
- 進行したとき
- 多くの葉がまるごと食べられ、ひどいと木全体の葉がなくなる。多くの葉に幼虫がいる。
イラガとは?
イラガは、幼虫が庭木や果樹などの樹木の葉を食害します。成虫はガで、葉に産卵し、ふ化した幼虫は周辺の葉を食べて成長します。幼虫はとげの生えた突起が体中にあり、独特の形をしています。成熟した幼虫は秋に繭(まゆ)をつくり、その中で越冬して春に蛹(さなぎ)になります。そして、初夏に成虫となって繭から出ます。
繭の形や模様は、イラガの種類によってやや異なり、卵形や扁平な楕円形などをしていて、樹木の幹や枝の分かれ目などにつくられます。
▼葉を食べ、ひどいと樹木が丸坊主に
若い幼虫は葉裏から表皮を残して食べるため、食害部分は白い斑点や白く透けた状態に見えます。成長した幼虫は葉全体を食べるので、多く発生すると葉がほとんどなくなり、樹木の生育が悪くなります。そのため、果樹では品質が低下し収穫量も減ります。庭木では観賞価値も下がります。
▼幼虫のとげには毒があるので注意
イラガには多くの種類があります。代表的な種類は、黄緑色の体の背中に、紫褐色のひょうたん形の模様があるイラガ、青色の斑点が連なっているヒロへリアオイラガなどです。イラガは7月から8月ごろに1回、ヒロへリアオイラガは6月から7月ごろと8月から9月ごろの2回、発生します。ともに幼虫のとげには毒があり、皮膚に触れると激しい痛みを感じるので、注意が大切です。
▼葉や枝を切り取って幼虫を処分する
苗木を購入するときは、繭がついていないか注意します。幼虫がいる初夏から秋は葉の食害痕の発生に注意し、見つけしだい幼虫がいる葉や枝ごと切り取ってすぐに処分します。捕殺作業の際はゴム手袋をはめるなどして、素手では幼虫に絶対触れないようにします。冬は、枝や幹についた繭を見つけて取り除きます。適用のある薬剤がある植物で、薬剤を使う場合は、幼虫が小さいうちに薬液を散布します。
- ※
- 薬剤を使用する際は、その薬剤の使用条件が、対象植物、病気や害虫、防除したい方法と合っていることを、ラベルなどで確認してください。

- イラガの幼虫。

- うずらの卵を小さくしたようなイラガの繭。

- ヒロへリアオイラガの幼虫。

- 扁平な楕円形をしたヒロへリアオイラガの繭。成虫が抜け出た穴があいている。
会員登録をすると、園芸日記、そだレポ、アルバム、コミュニティ、マイページなどのサービスを無料でご利用いただくことができます。
ピックアップ
会員限定
最新トピック&ニュース
新着日記写真

|

|

|
|---|---|---|
| 花しょうがの葉... 2024/04/24 | クレマチス モ... 2024/04/24 | 朝の散歩 2024/04/24 |

|

|

|
| セアノサスの蕾 2024/04/24 | “源氏名”変えて... 2024/04/24 | クレマチス 昇龍 2024/04/24 |