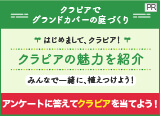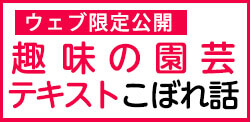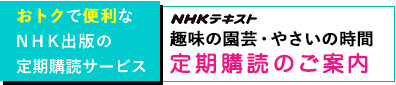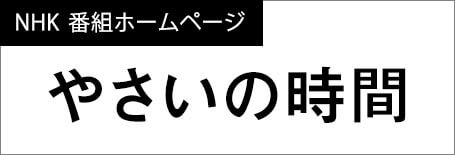シャクガ
善林六朗[園芸研究家]
- 初期症状
- 葉の縁がかすかに食害され、そこにきわめて小さく、髪の毛のように細い幼虫が多数いる。
- 進行したとき
- 多くの葉が食害されて枝だけになったり、花、蕾、果実なども食べられたりし、周辺に多数の幼虫が散らばっている。
シャクガとは?
シャクガは、幼虫が庭木などの樹木と草花を食害します。成虫は、広げた翅(はね)の幅が数cm前後あるガで、主に夜間に活動し、花の蜜を吸います。葉柄や枝の分かれ目付近などに、丸い卵をまとめて産みます。
幼虫は細長く毛のないイモムシです。移動するとき、全身を使って長さを測っているように見えることから、シャクトリムシ(尺取虫)と呼ばれています。体を空中や枝などの上にまっすぐ伸ばして動かず、枝の一部のように見せかけて、いるのがわかりにくい姿勢もとります。成熟した幼虫は土中で蛹(さなぎ)になり、羽化して成虫になります。冬は主に蛹が土中で越します。
▼葉や花などを食べる
主に葉を食害し、花、蕾、果実などを食べることもあります。そのため、多発すると、葉が食べつくされて枝だけになり、株の生育を著しく損なうだけでなく、果実の品質や草花などの観賞価値が下がります。
▼シャクガの仲間
シャクガには多くの種類があり、成虫の翅や幼虫の体は種類により、色、模様、大きさなどが違います。種類によって、食べる植物も異なります。代表的なものには、多種類の植物を加害するヨモギエダシャクやウメエダシャクなどと、一部の植物しか加害しないユウマダラエダシャクなどがあります。主に年に3~4回発生し、6月ごろから10月ごろにかけて幼虫の発生が多く、この時期に被害も目立ちます。
▼幼虫を捕まえて処分する
幼虫を見つけしだい捕殺します。雑草が繁茂すると発生しやすいので、除草に努め、近くに雑木林がある場合は、特に発生に注意します。適用のある薬剤がある植物で、薬剤防除を行う場合は、成熟した幼虫には防除効果が劣るので、幼虫が小さいうちに薬液を散布します。
- ※
- 薬剤を使用する際は、その薬剤の使用条件が、対象植物、病気や害虫、防除したい方法と合っていることを、ラベルなどで確認してください。

- ユウマダラエダシャクの成虫。翅を広げた大きさは40~45mm。

- ヨモギエダシャクの幼虫。成熟幼虫は体長55~60mm。キク、ダリア、ダイズ、アズキ、バラ、モモ、ミズキなどを食害する。

- ユウマダラエダシャクの幼虫。成熟幼虫は体長25~30mm。マサキ、ツルマサキ、ニシキギの3種類のみを食害する。

- ウメエダシャクの幼虫。成熟幼虫は体長30~35mm。ウメ、モモ、サクラ、マユミ、ボケ、ニシキギ、エゴノキなどを食害する。
会員登録をすると、園芸日記、そだレポ、アルバム、コミュニティ、マイページなどのサービスを無料でご利用いただくことができます。
ピックアップ
会員限定
最新トピック&ニュース
新着日記写真

|

|

|
|---|---|---|
| 3年生のフクシ... 2024/04/20 | アケビ 2024/04/20 | ようやく目覚めた 2024/04/20 |

|

|

|
| 盆栽 「クワ」実生 2024/04/20 | 今年のブルー 2024/04/20 | 柏の葉公園で講... 2024/04/20 |