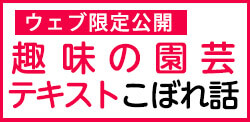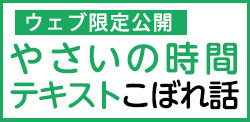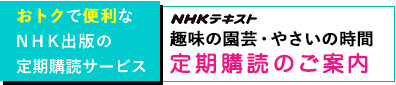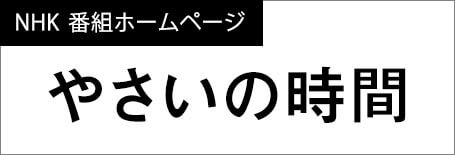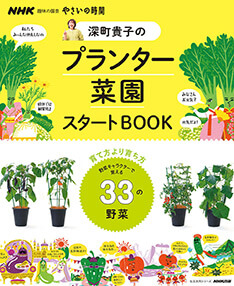- みんなの趣味の園芸
- 育て方がわかる植物図鑑
- ツワブキ
- ツワブキの育て方
ツワブキの育て方・栽培方法
栽培カレンダー

基本データ
 |
|||
| 園芸分類 | 山野草,草花 | ||
|---|---|---|---|
 |
|||
| 形態 | 多年草 | 原産地 | 日本列島(東北地方南部以南の本州、四国、九州)、朝鮮半島南部、中国東部~南部、台湾 |
 |
|||
| 草丈/樹高 | 20~50cm | 開花期 | 10月~12月 |
 |
|||
| 花色 | 黄,白,オレンジ | 栽培難易度(1~5) | |
 |
|||
| 耐寒性 | 普通 | 耐暑性 | 強い |
 |
|||
| 特性・用途 | 常緑性,カラーリーフ,日陰でも育つ,盆栽向き,初心者でも育てやすい | ||
 |
|||
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
日なたか明るい日陰で育てます。土質は問いませんが、水はけのよい土地を好みます。斑入り葉の園芸品種のなかには明るい日陰のほうがよいものもあります。
水やり
鉢植えは、表土が乾いたら十分に与えます。庭植えは、よほどの干ばつでもないかぎり水やりは不要です。
肥料
鉢植えは、植え替え時に元肥として、草花用のチッ素、リン酸、カリが等量の配合肥料や、油かすと骨粉の配合肥料などを5号鉢で三つまみほど施します。
4月から9月は月1回、草花用のチッ素、リン酸、カリが等量の配合肥料や、油かすと骨粉の配合肥料を施します。ただし、斑入り葉の品種のなかには、春に肥料が効きすぎると斑が現れにくくなるものがあります(特に曙斑のもの)。最初の新葉が成長している間は肥料を控えましょう。
庭植えは、追肥を少なめにするか、または元肥のみで問題ありません。
病気と害虫
病気:うどんこ病、斑葉病、褐斑病
うどんこ病は5月から8月に発生し、葉の表面に白い粉をかけたようなカビが生えます。あまり重症化はしませんが、気になるようなら発生した葉を切り捨てて再生させます。斑葉病と褐斑病はどちらも灰白色の円い病斑ができ、斑葉病では病斑の縁が褐色、褐斑病では病斑の縁が暗褐色で、のちに黒い点が現れます。どちらもあまり大発生しませんが、気になるなら発生した葉を切り捨てて再生させます。
害虫:キクスイカミキリ(シンクイムシ)
成虫は小さなカミキリムシで、4月から7月に葉柄に卵を産みつけます。幼虫が地下の根茎に向かって葉柄の内側を食い進み、最後には根茎の内部を食いつくします。春から夏にかけて、元気な葉の中にしおれたものが交じっていたら、その葉を根元からねじ切って幼虫を取り除きます。念のため、葉柄を裂いて中に幼虫がいるか確認し、いなければ根茎に入り込まれた可能性が高いので、株を掘り上げて根茎を割り、中にいる幼虫を捕殺します。完全に防ぐ方法はなく、周囲にキク科の雑草を生やさないことである程度少なくできます。
用土(鉢植え)
一般的な花壇用の草花培養土でよく育ち、特別のものを用意する必要はありません。庭植えは、10~20cmほど土を盛ってから植えると、生育がよくなります。
植えつけ、 植え替え
鉢植えの場合は、芽出し前の4月に、毎年か1年おきに植え替えます。鉢から地面に植え替えるだけなら、真冬を除けばいつ行ってもかまいません。
ふやし方
株分け:植え替えと同時に行います。古くなった根茎を、自然に分かれる部分で分けます。もしつながっていても、それぞれの芽に十分に根がついているのならナイフなどで切って分けてもかまいません。
タネまき:2月から3月にタネをまいてふやすこともできます。自然に実ったタネからは、親と変わり映えがしないか、劣ったものしか生まれません。好みの親を選んで交配しましょう。豆盆栽としてつくるなら小鉢にまくとよいでしょう。
根茎伏せ:葉のない古い根茎でも、生きていれば、植えておくと芽を出して新しい株ができます。
主な作業
枯れ葉取り:枯れ葉は取り除いて美観を保ちます。
花茎切り:タネをとる目的がないときは、花が咲き終わったら花茎を切り捨てます。
特徴
ツワブキは海沿いの草原や崖、林の縁に見られる常緑の多年草です。葉は革質でつやがあり、円くて直径20cm前後あります。新芽は茶色の綿毛に包まれていますが、成長につれて取れていきます。地下には短いワサビ状の根茎が連なり、大きな株になります。花は...
種類(原種、園芸品種)
-

-
‘牡丹獅子’
Farfugium japonicum ‘Botan jishi’ - 葉の縁が激しく波打ち(獅子葉)、全体に綿毛の多い園芸品種。花弁も波打つ。この品種をもとにして、いろいろな獅子葉の園芸品種がつくられている。
-

‘竜頭’
Farfugium japonicum ‘Ry〜zu’- 葉の表面にしわが寄り、突起を出す園芸品種。花もやや変形する。株が小さいときや根詰まり気味のときは特徴が出ないので、庭植えや大鉢に向く。
-

キモンツワブキ
Farfugium japonicum ‘Aureomaculatum’- ホタルツワブキとも呼ばれる。黄色いヒョウ柄のような斑が入る園芸品種。斑の部分が日焼けしやすいため、明るい日陰に向く。斑の密度や株の大きさに個体差がある。
植物図鑑の項目の見方について > 科名、属名の分類について >
◆植物には規制や保護が行われている種類、無断でふやして販売・譲渡を行ってはいけない登録品種などがあります。また薬剤の使用時は、ラベルをよく読み使用方法を守りましょう。
園芸を楽しむうえで知っておきたいこと >
さらに詳しく知りたい方におすすめの本
住宅周りにある日陰のスペースを、日の当たる時間などから4つのタイプに分けて解説。それぞれの日陰の特徴と、その日陰を改善する方法、植えられる植物を提案する。「日陰で育つ植物図鑑」の項では、約80種類を紹介。デッドスペースだった場所が、見応えのある植栽に変わる一冊。
ツワブキのそだレポ(栽培レポート)
ツワブキの写真
ツワブキに関する記事
-
変幻自在の名脇役 ツワブキの魅力
ツワブキはたいへん美しい植物です。光沢のある革質の葉は常緑で、グラウンドカバープランツとして重宝...
この植物名が含まれる園芸日記過去1年間
-
2024/04/11 白花ヒメシャガ開花写真1 白花ヒメシャガが開花した。 紙縒りのような頼りない蕾から咲いたとは思えない凝った花形 以前庭... (tix)
-
2024/04/09 どっちが主役?🌿草物盆栽を久し振りに作ってみた。 我家には、何種類ものスミレが咲いている🌿 雨の中、ピンクのヒラヒ... (虎吉)
-
2024/03/26 雨ですね~今朝ヒヨドリが来て伊予ミズキの蜜?を吸いに来ました。 写真1のマンリョウは食べづらいのか残したまま... (菊 一)
-
2024/03/25 ツワブキ我が家の庭のツワブキ。 仏壇のお花の中にツワブキの葉をいれて飾りました。 お彼岸にお参りに来た方か... (ちはこ)
-
2024/03/21 多肉の緊急避難3月21日(木)曇り時々晴れ 今日は、昨日の風と雨から一転して、良い天気。 昨晩外に出るといつもよ... (すてきなおじいちゃん)
- 園芸日記をもっと見る
関連するコミュニティ
- 関連するコミュニティはありません