Vandachostylis Charm ‘Blue Moon’
今年も咲きました。
今回は14輪です。
7月末には咲き始めていましたが、
9月2日現在まだ9輪残っていて、
この時期にしては長持ちしています。
以前の投稿で、
「花弁が反り過ぎて、花形がイマイチだったり、
花弁がすぐにゼンマイ状に巻いてしまったりするのは、
肥料のやり方とかに問題があるのかな~?」
みたいなことを書いていましたが、
過去の写真を見直していると、
そんなことよりも、
「どんな状態の株に咲いた花か」
の方が効いているような気がしてきました。
「若くて葉がピンとしている株」よりも、
「老成して葉がダランとしてきた株」の方が、
花弁の反りが強くなっているような気がする
ということです。
花びらは元々、葉が進化して変形したものだと
言われていますから、葉が強く反り返っている株だと、
花びらも同じように強く反り返るのではないか、
という、あくまで仮説です。
外の日差しや風雨や寒暖差に当てて育てていれば、
何年育てても、シャキッと引き締まった姿が
維持できると思います。
でも、室内の穏やかな環境で何年も育てていると、
株が大きくなるにつれて、
どうしても、こういうダランとした株に
育ってしまうのです。
なので、今の環境で育てる限り、
これはこういうものだと思うしかないようです。
今回は、花芽成長中も開花中も、
花芽が無い時と同じように液肥を与えてみましたが、
それで良さそうな感じです。
開花中も根と葉の成長は続いていますし、
花も長持ちしています。
昨年までの栽培では、
花芽が育ち始めて根や葉の成長が
少しばかり鈍る様子を見て、
肥料を減らしたり打ち切ったりしていましたが、
Blue Moon にとっては「余計なお世話」だったようです。
花芽に栄養を取られると他の成長が鈍るのは当然のことで、
それは栄養の配分が変わっているのであって、
栄養が要らなくなっている訳ではないんですね。
なのに、そこで肥料を減らしたりなんかするものだから、
そのせいで余計に成長が鈍ってしまうのです。
それを見てさらに肥料を減らして、
花が開き始める頃には完全に打ち切っていたので、
根の成長は完全に止まってしまっていました。
今回は、花芽が伸び始めてからも
通常通りの施肥を続けてみました。
そうすると、根や葉の成長は、
少し鈍りながらも、続くことが分かりました。
成長期・充実期・休眠期が分かれているタイプの蘭で、
休眠期に開花する場合に、
「開花期には肥料をやるな」と言われるのと、
バンダ類のように年間を通じて成長して
成長しながら開花もするタイプの蘭とを、
同じには考えない方がいいようです。
植込材なしで作っているバンダ類は、
肥料の蓄えが利かない分、
必要な時にちゃんと肥料をやってないと、
葉の長さが不揃いのいびつな株になりかねないので、
肥料不足には格別の注意が必要です。
「Van. Charm ‘Blue Moon’」関連カテゴリ
会員登録をすると、園芸日記、そだレポ、アルバム、コミュニティ、マイページなどのサービスを無料でご利用いただくことができます。
ピックアップ
-
 多肉植物の<写真&エピソード>を大募集!【6月10日(月)まで】
多肉植物の<写真&エピソード>を大募集!【6月10日(月)まで】
-
 趣味の園芸オンラインセミナー「猛暑に勝つ!」第2回〈今が大事!夏に備えるメンテナンス〉6月16日開催
趣味の園芸オンラインセミナー「猛暑に勝つ!」第2回〈今が大事!夏に備えるメンテナンス〉6月16日開催
-
 『趣味の園芸』6月号~梅雨に輝くアジサイと日陰の庭/夏はフロックスにおまかせ
『趣味の園芸』6月号~梅雨に輝くアジサイと日陰の庭/夏はフロックスにおまかせ
-
 夏野菜をスロースタートしたら、秋野菜はどうすればいいの?【やさいの時間6・7月号こぼれ話】
夏野菜をスロースタートしたら、秋野菜はどうすればいいの?【やさいの時間6・7月号こぼれ話】
-
 バラとの相性抜群&庭の頼れる植物【私の植物偏愛記・6月号こぼれ話】
バラとの相性抜群&庭の頼れる植物【私の植物偏愛記・6月号こぼれ話】
-
 『ガーデンライフ:夢の庭をつくろう』自分だけの理想の庭をつくる園芸シミュレーションゲーム発売![PR]
『ガーデンライフ:夢の庭をつくろう』自分だけの理想の庭をつくる園芸シミュレーションゲーム発売![PR]
-
 「PW春の感謝祭2024」開催!抽選で50名様にPWの植物が当たるそだレポ投稿キャンペーンも[PR]
「PW春の感謝祭2024」開催!抽選で50名様にPWの植物が当たるそだレポ投稿キャンペーンも[PR]
会員限定
最新トピック&ニュース
新着日記写真

|

|

|
|---|---|---|
| 室内から 2024/06/10 | いつも(月)は雨 2024/06/10 | 昨日の日記の1... 2024/06/10 |

|

|

|
| 夏向けの寄せ植え 2024/06/10 | 6/10 金陵辺の... 2024/06/10 | ギガンチウム ... 2024/06/10 |














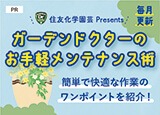
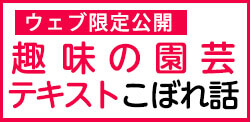


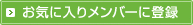


























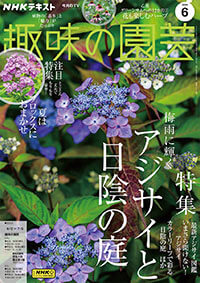
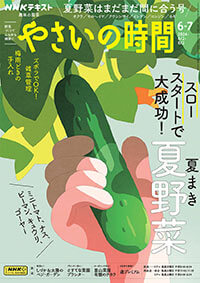


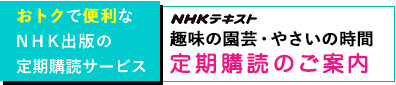
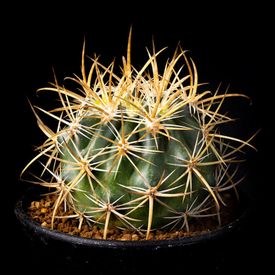
















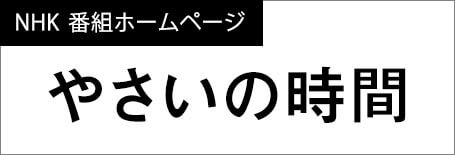











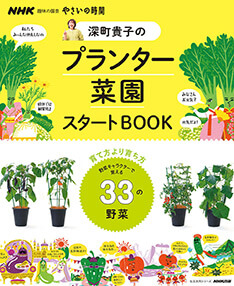


興味深く読ませていただきました。
返信するテキストの知識で頭でっかちにならず 植物と直接 対話を通して学びたいと思っているのですが そのお手本の様な日記ですね。
観察と記録、科学の基礎です。
お写真を拝見していると 少数精鋭、生え抜き という言葉が浮かびます。大切に育てられて幸せそうです。
いえいえ、少数ですが精鋭かどうか・・・(苦笑)
たまたま上手く行った時に投稿しているもので。
最近、肥料のやり方について
試行錯誤してみたくなったのは、
同じ植物についての話なのに
人によって意見が異なっている場合が結構あるのを
目の当たりにして、それぞれの意見が
どういう「文脈」で語られているかまでを考えないと、
真意が分からないのではないかと感じたからです。
「自分の文脈」、つまり、
自分の栽培環境で自分の植物で、
「今これやっていいのか?」が、
現物を見て判断できる目を養うことが
園芸の醍醐味なのだと思います。
「人によって意見が異なっている場合」を見た
というのは、例えば、私が持っている本に載っている、
寒蘭の秋(開花期)の肥料のやり方についてです。
ある本では、「花色の発色が冴えるためには
夏以降は肥料を切るべきだ」とあります。
一方、別の本では、「バルブの充実期と重なるので
肥料はやり続けるべきだ」とあります。
一見食い違う言い分ですが、
前者の本では、「固形肥料、有機肥料などの
いろんな肥料が使えるのでいろいろ工夫してみてね」
的な説明がされている後で、そう言っています。
後者の本では、「固形肥料や有機肥料は
上級者は上手く使って好結果を得ている人も多いけど、
初心者には加減が難しくて失敗の元になりかねないから
使わない方がいいですよ、化学肥料の液肥だけで
十分育ちますから、これからその前提でお話しします」
と初めに断ってから、書かれているのです。
前者のやり方には、
固形肥料や有機肥料は残効が長いから、
打ち切ったつもりでも少しは効き続けているという
含みが、実はあるんですね。
初心者向けの園芸書に書かれていることは、
カトレアとかバンダとかいった大きな括りの中で
(個々の品種というよりは分類群全体にまたがって)、
「満点は狙えないけど落第点だけは取らずに済む」
方法の指南ですから、とりあえず従っておけば、
枯らしてしまうことだけは避けられます。
でも、「その段階(初心者)」を卒業するのに、
教科書の言いなりになるのが本当にいいのかというと、
私はそうではないと思っています。
むしろ、「実際に枯らしてみる or
その寸前まで弱らせてみる」ことが、
最善の方法だと思うのです。
「やってはならないこと」を
一通り体験しちゃいましょう。
○○をやり過ぎちゃダメって言われても、
どの程度からがやり過ぎなのか、
自分の文脈の中で確認してこそ
真の納得に到達できますよ。
※コメントの書き込みには会員登録が必要です。